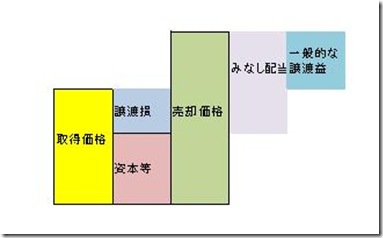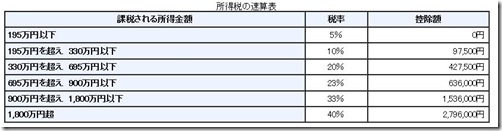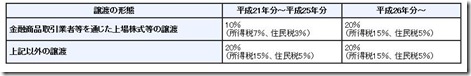みなし配当
グループ法人に該当しない
みなし配当の取り扱いは
① 譲渡損 と
② みなし配当
注意 みなし配当は 譲渡損と両建になります。
個人株主のみなし配当 課税関係
株式の譲渡損と
みなし配当課税
配当所得に該当して 総合課税となり
他の所得と合算され累進税率により課税されます。
自己株式とならない
第3社への譲渡の場合は
株式の譲渡所得として分離課税となります。
その場合の譲渡益は
売却価格-取得 税率 所得15%住民5%)
の分離課税 で非常に低税率です。
そこで グループ法人を利用して
節税を図ります。
迂回 自己株式
株主は A社の株式を A社に買い取らせ 資金を調達したいが
直接 A社に売却すると 税金が多額になるので B社に売却します。
B社は それを A社に買い取ってもらいます。
B社の処理
みなし配当と譲渡損の両方認識
受取配当等の全額益金不算入で
いいとこどりで 譲渡損のみ で
所得が圧縮できる。
もともとの株主は 株式の譲渡所得課税
めでたし めでたしです。
しかし 税務側は 迂回 自己株式として
行為計算を否認する可能性も指摘されてますが
完全支配関係の会社からの自己株式は
受取配当等の全額益金不算入の規定が働き
いいところ取りはできなくなっています。
注意
相続人が取得した自己株式の譲渡についは
みなし配当課税を行いませんので
株式の分離課税 で 取得費加算の特例があります。
迂回 譲渡させる必要はありません。
発行法人への株式譲渡
完全支配関係にある法人間の取引では
発行法人へ株式譲渡は譲渡損益を発生しない
仕組みを作り上げ
税制が改正されました。
従来の規定では 迂回 自己株式に
該当しない場合は いいとこどりができていましたが
自己株式も他の資産の譲渡と同じく
損益を繰り延べることに改正されています。
みなし配当については論点が多く
今後も紆余曲折の改正が入ると思われます。
タグ
2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制
中小法人の特例
資本金1億円以下の法人 「中小法人」
については
- 軽減税率
- 留保金課税の不適用
- 貸倒引当金の法定繰入率
- 欠損金の組戻還付
- 交際費の損金算入限度額
などの優遇税制になっています。
これが グループ法人の場合には 自らの資本金の規模に加えて
親会社の資本金が5億円以上の場合には
中小法人の優遇税制が受けられません。
資本金が1億円以上5億円未満の場合
単体課税の場合は上記の中小法人の特例有り
連結納税の場合は 特例適用なし
中小法人等の特例も適用なし
上記の中小法人の特例以外に
- 中小企業投資促進税制
- 教育訓練費の特別控除
- 少額減価償却資産の取得価額の特例
なども適用できません。
タグ
2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制
受取配当等の全額益金不算入
100%支配関係にある子法人からの配当は
間接的に行われている事業からの資金移動に
過ぎないので所得と認識することは好まなくない
との理由で改正されました。
利便性
グループ内での資金集中など戦略的なグループ企業としての
フリーキャシュシュフローが増加させることが可能になりました。
対象は 配当の計算期間グループ法人であることを継続していることです。
現物配当の取扱
適格現物配当の譲渡損益の繰延
現物配当とは 剰余金の分配 または みなし配当により
金銭以外の資産を交付することです。
完全支配関係にある内国法人で行われるものを
適格現物配当として 譲渡損益を繰延べます。
例
A社 100% ⇒ B社 100% ⇒ C社
A社の子会社 B社 A社の孫会社C社である場合に
B社が C社株式を A社に現物配当した結果
A社 100% ⇒ B社
100% ⇒ C社
の関係が築けます。
現物配当に関しては 譲渡損益を認識しないことと
源泉徴収も行わないことになりました。
タグ
2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制
寄付金の取扱
グループ内での寄付金の取り扱いについては
- 支出法人側では 全額損金不算入
- 受け入れた法人側では 全額益金不算入
となります。
グループ内での資金の移動に関しては損益とならないので
資金移動が行い易くなりました。
完全支配関係にある法人に限定
同族関係者が株主であるグループ法人間の
寄付金については
資金を移動しての株価対策と利用防止目的から
法人による完全関係に限定されています。
タグ
2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制
資産の譲渡の繰延
対象資産
- 固定資産
- 販売用を含む土地
- 有価証券、金銭債権および繰延資産
除外
棚卸資産、帳簿価格1千万円未満の資産を除きます。
影響
含み損を抱えた不動産を保有している場合は
期末近くに、決算対策としてグループ内で譲渡しても
損失を実現させることができなくなりました。
譲渡損益の認識のタイミング
- 譲り受け法人側の譲渡 減価償却 評価替え
貸倒 除却など その他政令で定める事由が生じたとき
- 完全支配関係を有しないこととなったとき
減価償却などはその都度費用化させることとなります。
グループ内で再譲渡した場合
- B社⇒C社へ譲渡した場合の譲渡損益については
- さらに C社⇒D社へ譲渡した場合には
B社の譲渡損益は認識される。
事務負担の軽減から譲渡先はグループ内であっても
譲渡損益は認識することになっております。
(実務上の抜け道を作ってあります。)
含み資産を実現させることは グループ内で
2度譲渡することで可能になっています。
考えた人が偉いんでしょうか?
タグ
2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制